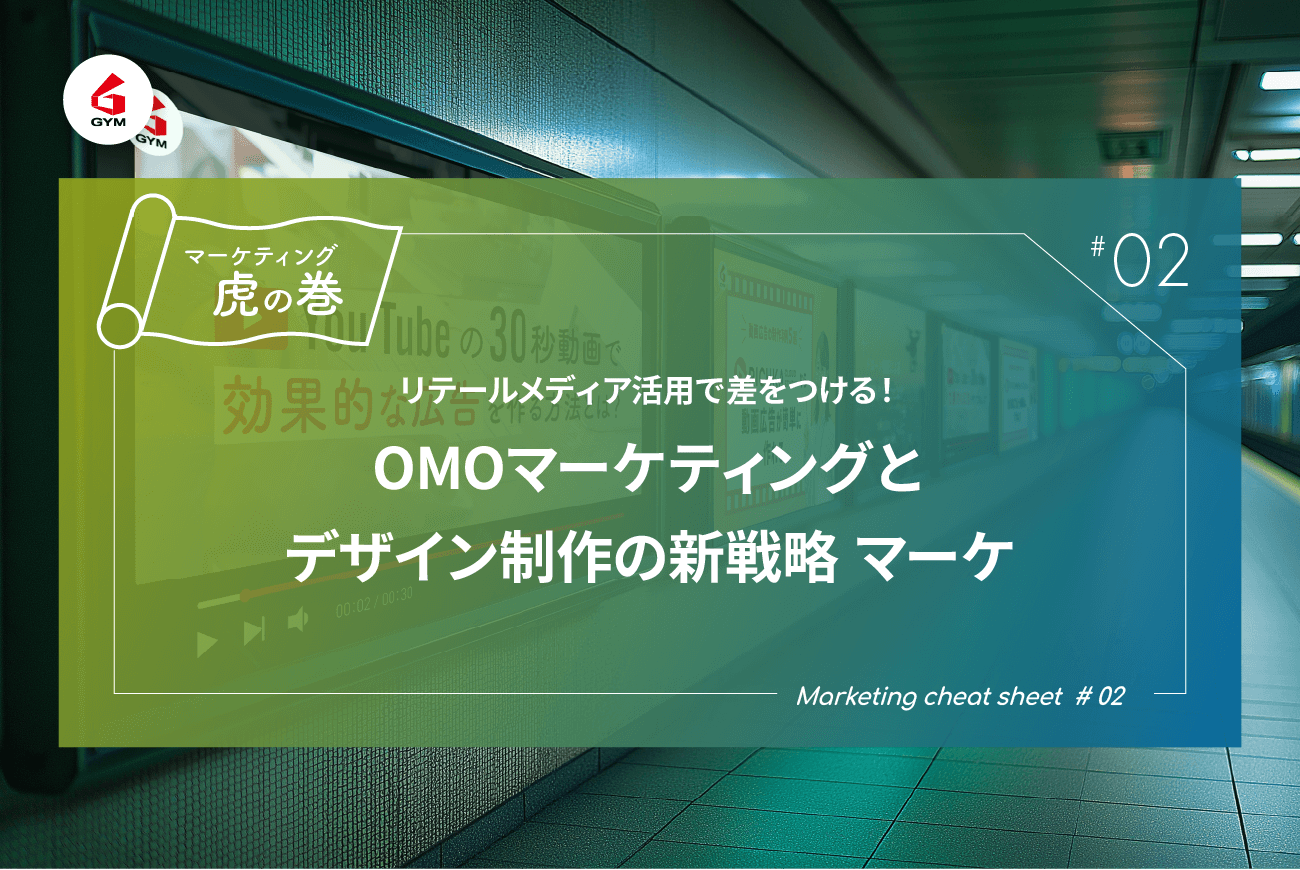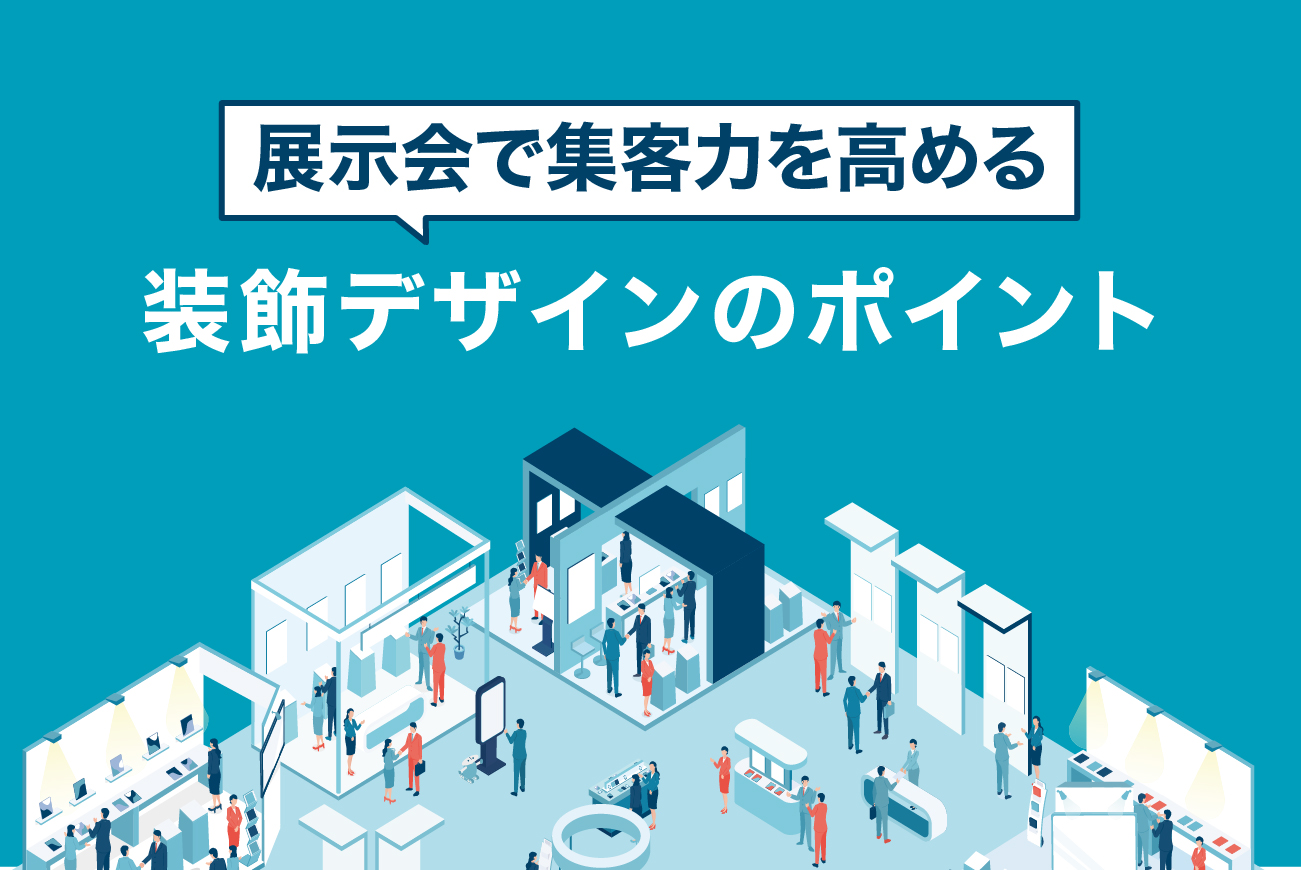1. デザインを「なんとなく」で選んでいませんか?
「デザインは良いのに、なぜか成果(売上・問い合わせ)が出ない」 「Webサイトをリニューアルしたが、担当者の好みや主観で方向性が決まってしまったように感じる」
企業の広告・マーケティング担当者として、このような悩みを抱えていませんか?
多くのビジネス現場で、マーケティングとデザインは分離して考えられがちです。しかし、ビジネスの成果を最大化するためには、この2つを融合させる「マーケティング視点のデザイン」が不可欠です。
「なんとなくかっこいいから」「流行っているから」でデザインを選んでしまうと、ビジネスの成果につながりません。
本記事は、貴社のビジネスが目指す「成果」を達成するため、「戦略的デザイン」とは何か、その考え方(定義)から具体的な実践手段までを解説します。マーケティングとデザインの関係性、そしてそれらを活用する方法を理解することで、貴社の事業は確実に前進します。
2. よくある失敗:「マーケティング」と「デザイン」が分離する理由

なぜ「デザインは良いのに成果が出ない」という状況が起きてしまうのでしょうか。それは、戦略と実行が分断されているからです。私たちデザイン会社が現場で直面する、典型的な失敗パターンをご紹介します。
パターン1:「かっこよく」「良い感じに」という抽象的な依頼
「ターゲットに映える動画を」「とにかくかっこよくしてほしい」
こうしたご依頼の裏には、「競合他社より見栄えを良くしたい」という切実な思いがあるかもしれません。しかし、もし発注側と制作側で「何を達成するか(評価軸)」が共有されないまま制作が始まると、「なんとなく」のデザインが生まれます。
特に予算や納期がタイトな場合、クライアントの優先度が「納期の短縮」になるのは仕方のないことです。 私たちもプロとして、限られた時間の中で最良のデザインワークを提供します。そこには、体系的な分析(上流工程)に割く時間こそありませんが、過去の経験則から導き出した「成果につながるマーケティング視点」も可能な限り絞り出し、反映させています。
ただ、制作側がクライアントのビジネスに対し本質的に貢献できるのは、視覚的なかっこよさを追求するだけではない、という点も事実です。多くの場合、もう一歩踏み込んだ「戦略の共有」、すなわち目的やターゲットに関する内部での認識共有と、制作側とのコミュニケーションこそが、成果を最大化する鍵となります。
パターン2:マーケティング先行型
戦略やデータ分析は完璧で、分厚い資料が用意されている。しかし、最終的なクリエイティブ(Webサイト、広告バナー、動画)がターゲットの「感情」を動かせず、誰にも刺さらない。
これはマーケティング思考が先行し、デザインの力を軽視した結果です。マーケティングのロジックは重要ですが、それをユーザーに「自分ごと」として伝える翻訳機能=デザインがなければ、商品や製品の魅力は半減してしまいます。
パターン3:デザイン先行型
見た目は美しい、あるいは流行の表現を取り入れているが、企業の「目的(KPI)」や「ターゲットの課題」を解決するという設計思想が抜け落ちているケースです。
これは、デザイナーが持つ優れたスキルや美的感覚が、ビジネス全体の目的と連携していない状態です。美しいものを作ること自体は価値ですが、これではビジネスにおけるデザインの役割を十分に果たせません。
3.「マーケティング視点のデザイン」とは何か?
では、私たちが提唱する「マーケティング視点のデザイン」とは何でしょうか。
それは、デザインを「装飾」ではなく「戦略の可視化」と捉えることです。
マーケティングが「誰に(Target)」「何を(Value)」を決定する「設計図」だとすれば、デザインはその設計図を「どう伝えれば(Creative)」ターゲットの心を動かし、行動(成果)につなげられるかを最適化する「実行」そのものです。
この「設計図」と「実行」が連携して初めて、ビジネスは成果を生み出し始めます。
デザインとブランドの関係性
特に重要なのが、ブランドとデザインの関係です。マーケティングが「何を約束するか」を決める戦略なら、デザインは「その約束をどう表現し、顧客との信頼を築くか」という戦術です。
ロゴ、Webページ、商品パッケージ、SNSの投稿画像まで、顧客が触れるすべてのデザイン要素が一貫したメッセージを発信し続けることで、初めて強力なブランドイメージが顧客の心に蓄積されます。マーケティング視点のデザインとは、このブランド構築活動そのものであり、企業の信頼を形作る重要な施策なのです。
制作会社が持つべき視点
私たちの強みは、クライアントの目的(KPI)に対し、「なぜこのビジュアルなのか」「なぜこのコピーなのか」を明確に言語化できることです。これは、マーケティングとデザインの違いを理解し、両者を「つなぐ」思考があるからこそ可能になります。
4. マーケティングがデザインをどう導くか? 戦略と実行

デザインのプロセスは、手を動かす(描画する)ずっと前から始まっています。デザインに着手する「前」に必要なマーケティング的思考、つまり「設計図」の作り方を見ていきましょう。これらの上流工程が、最終的なデザインの効果を左右します。
目的(KGI/KPI)の明確化:何を達成するか
そのデザインで「何を達成したいのか」というKPI設定を明確にします。これは事業課題から落とし込まれるべきです。
例: 事業課題が「新規顧客の開拓」であれば、KPIは「Webサイトからの問い合わせ数 20%向上」かもしれません。
例: 事業課題が「既存顧客のリピート率向上」であれば、KPIは「メルマガ経由の購買率 5%改善」かもしれません。
もっと身近な例では、飲食店の「売上UP」というKPIに対し、「メニュー」や「ポスター」「看板」のデザインを最適化することも、マーケティング視点のデザインが直接成果に結びつく好事例です。
目的が「認知拡大」なのか「CVR改善」なのか「ブランドイメージの刷新」なのかによって、デザインの方法は全く異なります。
例えば「イベント集客」を成功させるには、開催の「目的」を明確に設計し、そこから逆算してターゲットに響くデザイン(Webページ、チラシ、SNS広告など)を実行することが重要です。
ターゲット(ペルソナ)理解:「誰に」届けるか
「誰に」届けたいのか。対象となるユーザーの具体的な設定(ペルソナ)を深掘りします。
単なる年齢や性別といった属性情報(デモグラフィック)だけでなく、その人が持つ価値観、悩み、情報収集の方法(利用メディアなど)、購買に至る心理(インサイト)までを深く理解します。
このターゲット理解が浅いと、どんなに美しいデザインも「誰にも響かない」ものになってしまいます。ターゲットに向けた最適なコミュニケーションを設計する上で、最も重要なポイントです。
自社の強み(USP)と競合分析:「なぜ」選ばれるか
「なぜ」自社が選ばれるのか。市場や競合の中で、どのような「立ち位置」をデザインで表現すべきかを定めます。
競合他社のWebサイトや広告コンテンツ、最新の市場環境を分析し、技術的な優位性、価格、サポート体制、ブランドイメージなど、自社が持つ独自の強み(USP = Unique Selling Proposition)を明確にします。
例えば、オンラインとオフラインを融合させる「OMOマーケティング」や「リテールメディア」の活用といった最新の市場戦略において、デザインがどのような役割を果たすべきかを考えることも、競合分析の重要な視点です。
その強みを、ターゲットに最も響く形で伝えるデザインを開発します。例えば、競合が「価格」で押しているなら、自社は「信頼感」や「専門知識」を前面に出すデザインを採用する、といった施策が考えられます。
5. デザインがマーケティングをどう加速させるか? 実行と成果
完璧な「設計図(マーケティング戦略)」も、それが伝わらなければ意味がありません。戦略を「成果」に変えるため、デザインが果たす具体的な役割と、その効果を解説します。
ブランディング(世界観の構築)
ロゴ、カラールール、フォントで「企業らしさ」を演出し、一貫したブランドイメージを顧客の記憶に蓄積させます。
これはデザインの領域の中でも特に「感覚」が問われる部分ですが、マーケティング視点があれば、「なぜこの色なのか(ターゲットが好む色だから)」「なぜこの書体なのか(信頼感を伝える書体だから)」をすべて説明できます。一貫したブランド体験は、顧客のロイヤリティを確実に向上させます。
この「世界観の構築」は例えば、オフラインの重要な顧客接点である「展示会」のブース装飾デザインなども、マーケティング戦略と連携した重要なブランディング活動です。
これはBtoC(一般消費者向け)に限らず、BtoB(企業間取引)においても同様です。例えば、デベロッパー(建設・不動産)企業がホームページで自社のプロジェクトを紹介する際、集客(マーケティング)とブランディング(デザイン)を両立させることが、企業の信頼獲得に直結します。
UX/UIデザイン(顧客体験の最適化)
Webサイトやアプリで、ユーザーが「迷わず」「心地よく」目的(購入・問い合わせ)までたどり着ける導線を設計します。
特にデジタルが中心の現代(2025年以降もこの環境は続くでしょう)において、UX(顧客体験)は商品や製品そのものと同じくらい重要です。デザインは、ユーザーの行動や心理に対する深い知識と技術を活用し、「使いやすさ」「分かりやすさ」を追求します。優れたUX/UIは、Webページの離脱率を下げ、CVR(転換率)に直接的な影響を与えます。
情報デザイン(伝達力の最大化)
複雑な情報やサービスの魅力を、図解(インフォグラフィック)や動画で「瞬時に」理解できるように整理・表現します。
BtoBの難解な製品説明や、サービスの特徴一覧も、デザインの力で「一目でわかる」コンテンツに変えることができます。これらは、情報を伝えるための強力な手段です。
特に近年では、複雑な情報やデータを「インフォグラフィック動画」として表現する手法も、マーケティングの成果に大きく影響を与えています。
デザイナーが持つ情報整理のスキルと、ターゲットの理解度を想像するマーケティング視点の両方が必要です。
近年注目される「デジタルサイネージ」なども、単に映像を流すのではなく、設置場所の環境やターゲットの行動を分析(マーケティング)した上で、瞬時に情報を伝えるデザインを設計することで、その効果が最大化されます。
最新のメディアや表現技術を積極的に取り入れ、最も適切な方法で情報を伝える工夫が求められます。
クリエイティブの重要性
私たちはクリエイティブ集団として、論理的な設計(マーケティング)だけでなく、こうした「感覚による視覚的な気持ちよさ」「感情の動き方」「コピーの文字面」といった、人の心を動かすクリエイティブ面も同様に重視しています。論理だけでは人は動かず、感情だけでも成果は出ません。この両立こそがプロの仕事です。
6.【実践】マーケティング視点のデザインを実現するプロセス
では、具体的にどうすれば「マーケティング視点のデザイン」を実現できるのか。私たちがデザイン会社として実践している「デザイン プロセス」をご紹介します。
Step 1:戦略的ヒアリング “何を変えたいか”を聞く
私たちが最も大事にしているステップです。 私たちはクライアントに「何を作りたいですか?」とは聞きません。 「(デザインを通じて)何を変えたいですか?」「どんな課題を解決したいですか?」と、真の課題を一緒に探すところから始めます。
デザインの発注で失敗しないコツは、この「目的の共有」にあります。ここでクライアントのビジネス全体の課題認識を共有することが、後工程すべての土台となります。

Step 2:上流工程の設計 ワークショップ・分析
ご予算と時間に理解のあるクライアントとは、デザイン制作の前に「カスタマージャーニーマップ」の作成や「ワークショップ」といった活動を実施します。
- カスタマージャーニーマップ: 対象ユーザーが商品を認知し、興味を持ち、購買し、ファンになるまでの行動と思考、感情の「旅」を可視化します。これにより「どのタイミングで」「どんなコンテンツ(情報)」をデザインで提供すべきかが明確になります。
- ワークショップ: クライアントの社内担当者様だけでなく、関連部署の社員の方も巻き込むことで、部門間の認識のズレをなくし、目標を一つにします。これらの活動を通じて率直なコミュニケーションを行うことで、表面化していなかった真の課題や、事業の強みを再発見する効果があります。過去の類似事例なども参考にしながら、最適な戦略を探すステップです。
Step 3:情報設計とクリエイティブ制作
Step 1, 2で定義した「戦略(設計図)」に基づき、ワイヤーフレーム(Webの骨組み)の作成や、ビジュアルコンセプトの策定を行います。 この段階で「なぜこのビジュアルか」が言語化されているため、手戻りや「なんとなく」の修正が劇的に減ります。ここでデザインは「感覚」から「ロジック」へと昇華されます。
Step 4:効果測定とデザイン改善
デザインは「作って終わり」ではありません。 Webサイトの公開後、動画の配信後、アクセス解析やヒートマップツール(Google AnalyticsやClarity, Mouseflowなど)を活用し、「設計図通りにユーザーが動いたか」を検証します。
デザインを単なる「経費(コスト)」ではなく、未来の価値を生む「戦略的資産」と捉え、継続的に改善(投資)を続けることが、成果を最大化する鍵です。デザインの効果を測定し、次の施策に活かす。このPDCAサイクルこそがマーケティング視点のデザインの神髄です。
7. まとめ:「なんとなく」のデザイン発注から脱却するために
以上のように、「マーケティング視点のデザイン」とは、ビジネスの「戦略(設計図)」と「クリエイティブ(実行)」という異なる要素を高いレベルで融合させることです。
最適なパートナーとなる「デザイン会社の選び方」を探す企業の担当者様へ。 その会社が、「何を作れるか」だけでなく、「貴社の課題をどう解決しようとしているか」を見てください。
私たちは、貴社の「“何を変えたいか”」に耳を傾け、「なぜこのデザインなのか」を言語化し、マーケティング(論理)とクリエイティブ(感情)の両面から成果にコミットするパートナーです。
「戦略から考えるWeb・動画・グラフィック制作に興味がある」 「自社のマーケティング課題をデザインで解決したい」 「まずは、何を変えたいかを聞いてほしい」そうお考えの担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。 貴社のビジネス成長というゴールを共に目指す「戦略的デザイン」をご提案します。